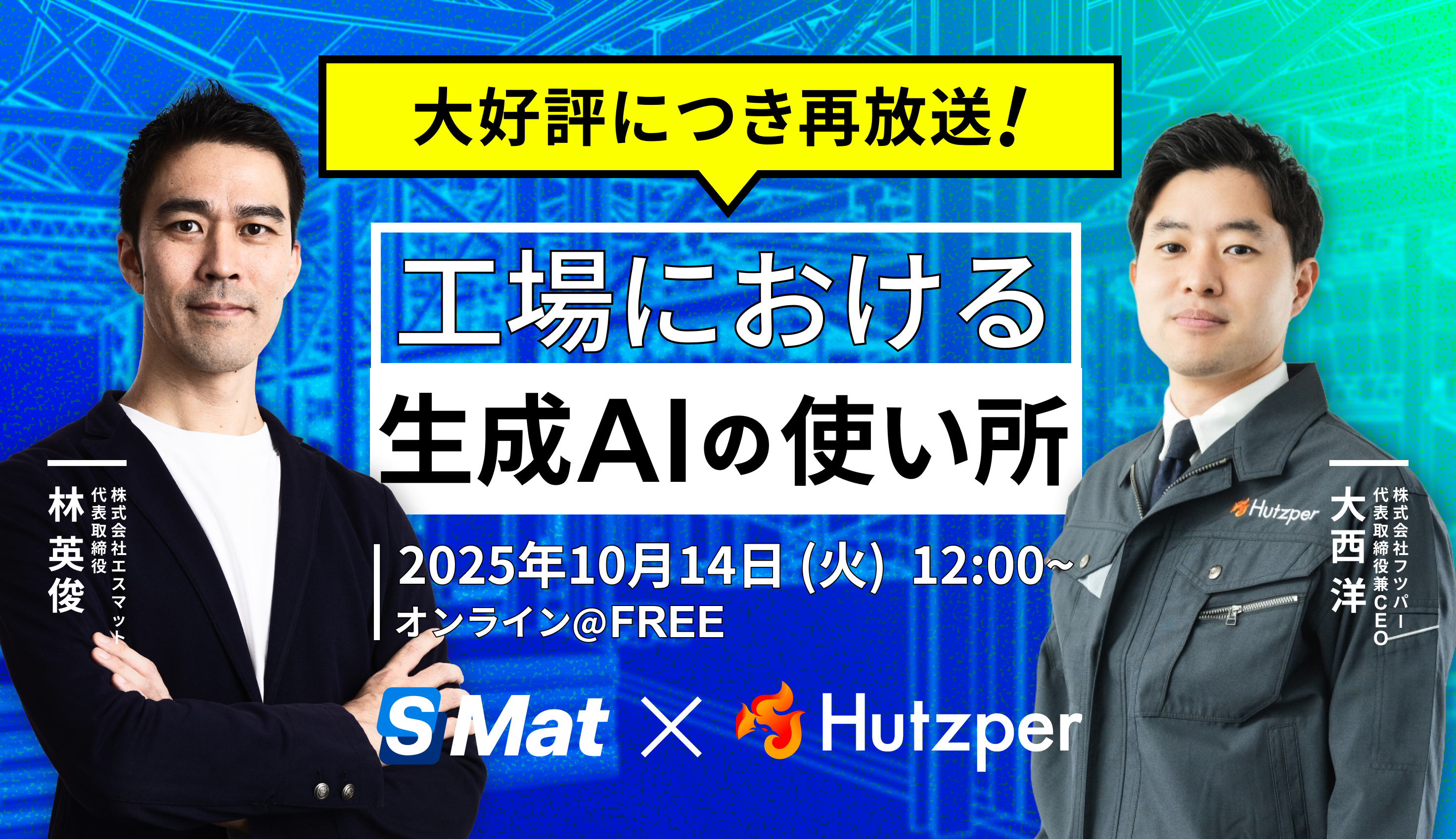在庫管理術
SKUの意味や重要性とは?最適な管理方法と注意点を解説

製造現場で起きる混乱は、SKUの設計の曖昧さが原因になっていることがあります。
「同じ部材なのに名称が統一されていない」
「仕様違いの識別が甘く、払い出しミスが起きる」
「棚卸のたびに在庫差異が出る」
SKUはJANコードや仕入先型番とは異なり、自社が在庫管理のために設計する内部コードです。自由に作れる反面、ルールが曖昧なまま点数が増えると、問題が必ず発生します。
この記事では、製造業向けの在庫管理改善に携わってきた筆者が、現場で使えるSKU設計の型を解説します。読み終える頃には、自社の部品マスタ・品目マスタを正しく整備し、生産や調達の精度を高めるためのSKU運用の芯が確立できるようになるはずです。
この記事でわかること
- SKU・JANコード・品番の明確な役割の違い
- すぐに使えるSKU命名規則テンプレートの作り方
- ERP・WMS・生産管理システムとの連携を阻害するNG文字と回避策
SKUとは?意味と重要性を3分で理解
SKU(エス・ケー・ユー)とは、Stock Keeping Unit(ストック・キーピング・ユニット)の略称で、日本語では「在庫保管単位」と訳されます。SKUは在庫を把握する上でこれ以上分けられない単位を指します。

Tシャツを例に挙げると消費者から見れば同じデザインの商品ですが、倉庫管理では次のように扱います。
赤 × Sサイズ
赤 × Mサイズ
青 × Sサイズ
青 × Mサイズ
色やサイズが1つでも違えば、保管場所も在庫数も別々に管理する必要があります。
この属性ごとに分かれた単位こそがSKUです。
製造業でいえば、同じ部品でも 材質違い・長さ違い・ロット違い・定格違い があれば、すべて別SKUになります。
SKUとアイテムや品番との違いは?
物流や小売の現場では、アイテムとSKUとを明確に区別します。
- アイテム:商品の種類そのもの。デザインや型番単位。
- SKU:アイテムをさらに細分化した、サイズ・カラーごとの単位。
もしSKU単位で管理せず、品番だけで管理してしまうとどうなるでしょうか? 「Tシャツが全部で100枚ある」とは分かっても、「Sサイズがあと何枚あるか」が分からず、欠品や在庫がないのに注文を受けてしまう売り越しの原因になります。
JANコードとSKUの違い【比較表あり】
「JANコードとSKUは何が違うのか?」という質問もよくいただきます。
一般財団法人流通システム開発センター(GS1 Japan)によれば、JANコードは「どの事業者の、どの商品か」を識別するための国際標準のコードです。これに対し、SKUはあくまで自社の中で在庫を管理するためのコード。両者の違いを表で整理しました。
|
項目 |
JANコード (GTIN) |
SKU (自社商品コード) |
|
役割 |
世界共通(販売・POS用) |
社内管理用(在庫管理・発注用) |
|
発行元 |
GS1 Japan(申請が必要) |
自社(自由に設定可能) |
|
変更 |
原則不可 |
運用に合わせて変更可能 |
|
主な用途 |
レジ通過、他社とのデータ交換 |
倉庫内棚番管理、ピッキング、発注 |
【実例付き】失敗しないSKUの付け方・命名規則 3つの鉄板パターン
SKUは自社で設計できますが、自由度が高いぶん「どのように付ければ後で困らないのか?」という悩みが出てきます。場当たり的に命名すると、
-
Excelで並べ替え・抽出ができない
-
ピッキングや現場作業で取り違いが発生する
-
システム導入後にマスタを作り直す羽目になる
といった問題が発生します。多くの企業で実際に活用され、運用を始めてからも困りにくいと評価されている代表的なSKU命名パターンを3つに整理しました。
自社の商品構造・部品構成に最も近いパターンを選び、そのままフォーマットとして採用するだけで、SKUの混乱を予防できます。
パターンA:量産部品向け(品番 + 属性型)
同じ品目でも 材質・サイズ・表面処理など、明確な属性違いが存在する部品・材料に最適です。
-
基本構造:
[品番]-[属性A]-[属性B] -
作成例:
BOLT-M6x50-SUS (=M6×50のボルト/SUS材)
【ポイント】
品番 → 属性 → もうひとつの属性の順で ハイフン(-)区切りにすると、SKUを見ただけで仕様が把握でき、払い出しミス・工程取り違え・検査漏れを防ぐ効果が高くなります。材質・長さ・表面処理など、現場が混乱しやすい属性をコード化するのが鉄則です。
パターンB:仕入れ品・完成品向け(メーカー型番活用型)
仕入れ商品や完成品を多く扱い、メーカー型番が信頼できる場合に最も効率の良い方式です。
-
基本構造:
[メーカー略称]-[メーカー型番]-[自社識別コード] -
作成例:
OMR-E3Z-D62-SUS(オムロン製光電センサ/SUS取付仕様)
【ポイント】
メーカー型番イコール仕様情報なので、発注・検品・補充がスムーズです。ただし同じ型番が他メーカーでも存在することがあるため、メーカー略称と自社用識別子をつけて SKUの一意性を担保します。
パターンC:一品物・試作・治具向け(年月 + 連番型)
金型・治具・試作品・個別仕様の特注品など、製造の都度仕様が異なり、同じSKUが発生しないアイテムに最適です。
-
基本構造
[製造年月/登録年月]-[連番] -
例:
2311-0052(=2023年11月登録の52番目)
ポイント
属性情報を SKUに含めず、あくまで個体識別番号としてSKUを付番する方式です。設定すると登録が簡単、古い治具・金型を見つけやすい、使用履歴・貸出管理・棚卸が正確になるというメリットがあります。属性はSKUに埋め込まず、マスタ側の項目で管理します。
✍️ 筆者の経験からの一言アドバイス
SKUの属性の並び順は倉庫の棚に部品をどう並べているかに必ず合わせてください。
製造業の現場でも、SKUの並び順をどうするかで議論が起きがちです。
私自身、過去に生産管理・倉庫チームと調整したことがありますが、最終的に行き着いた答えはとてもシンプルで、正解は、現場の棚、つまりロケーションに聞くことでした。SKUの並びとロケーションを合わせるだけで、払い出し・補充・棚卸の作業時間が驚異的に短縮できます。
関連記事:棚の在庫管理の方法とは?>>
SKU設定で避けるべき禁忌文字とは?
SKUは登録後に変更が難しいため、最初からシステムエラーを起こさない文字だけで構成することが必須です。
一度運用が始まると、商品マスタや生産管理システム、WMS、バーコードなど多くの領域に紐づくため、変更コストが非常に大きくなります。
だからこそSKUで最初から使ってはいけない文字を明確にし、禁忌を徹底しておく必要があります。以下製造業・物流・ECで共通するNG文字をまとめました。
【NG例1】全角文字とスペース
× 悪い例:TSHIRT RED S(全角スペース)
× 悪い例:TSHIRT RED S(半角スペース)
【理由】
在庫管理システムやCSV連携では、空白を区切り文字と誤認するケースがあります。結果、TSHIRTRED S のように勝手につながったり、項目がずれて読み込まれたりします。また全角文字はシステム側が処理できず、想定外のエラーを引き起こす原因にもなります。
【対策】
区切り文字は半角ハイフン(-)に限定するのが最も安全です。アンダーバー(_)も使用できますが、視認性が下がるため推奨ではありません。
【NG例2】視認性の悪い文字
× 悪い例:A01-I(ゼロとオー、イチとアイが混在)
【理由】
倉庫・工場では、薄暗い場所や作業スピードの速い場面が多く、
- O(オー)と0(ゼロ)
- I(アイ)と1(イチ)とl(エル)
などは肉眼で区別しにくく、棚卸間違いや誤払い出しの主要因になります。
【対策】
最初から O, I, l, Z, 2 などの紛らわしい文字は欠番に設定し、やむを得ず使う場合は、
- 桁数を固定する
- 先頭に付ける識別のための固定文字、プレフィックスを決める
などの対策で文字列から判断できるようにします。
【NG例3】機種依存文字・日本語
× 悪い例:T-SHIRT(赤)①(丸数字・日本語)
【理由】
丸数字(①)、ローマ数字(Ⅱ)、半角カタカナなどの機種依存文字は、CSV出力・システム連携・海外製ソフトへの取り込み時に文字化けするリスクが高く、t-shirt(赤)? のように意図しない変換が発生します。漢字・ひらがなもシステムによってはエラーの原因になります。
【対策】
SKUは半角英数字(A-Z, 0-9) + 半角ハイフン(-)のみで構成するのが鉄則です。
ExcelでSKUを自動生成する実践テクニック【テンプレート】
「ルールは決まったけど、品目が1,000点もあり、手入力でSKU設定は無理」
ご安心ください、そのお悩みはExcelで一気に解消できます。
Excelを使えばSKU設定は一瞬で終わります。むしろ手入力はタイプミスの温床です。以下の手順で、関数を使って自社用テンプレートを準備しSKUを自動生成しましょう。
【手順】
- A列~C列に要素を入力する
- D列に関数を入力する
- D2セルに以下の数式を入力します。
- オートフィルでコピーする
- 「値」として貼り付ける
この手順をステップバイステップで図解を交え説明します。
ステップ①A列〜C列に要素を入力する
要素を禁忌文字を避けて入力します。
• A列:品番(例:TS001)
• B列:カラー(例:RED)
• C列:サイズ(例:S)
ステップ②D列に関数を入力する
D2セルに以下の数式を入力します。
• =A2 & "-" & B2 & "-" & C2

ステップ③オートフィルでコピーする
D2セルの右下をダブルクリックして、下までコピーします。
ステップ④値として貼り付ける
数式のままだと使いにくいので、D列をコピーし、「形式を選択して貼り付け」→「値」で確定させます。
分野別SKU運用のポイントと注意点
商材によって、SKU管理の悩みどころは異なります。 ここでは課題の多い2つの分野について、運用のコツを紹介します。
加工部品:SKUが肥大化しやすい分野
金属部品や樹脂加工品のように、同じ品番でも材質・長さ・表面処理・精度等級といった仕様違いが多い領域では、SKUが増えすぎて管理が追いつかなくなることがあります。いわゆるSKU増殖(SKU proliferation)と呼ばれる現象で、現場での取り違えや生産計画の乱れを引き起こす代表的な要因です。
SKUそのものはシンプルに保ち、詳細情報は図面番号や属性欄に委ねることで、SKUの数を増やしすぎず、現場が迷わない仕組みをつくれます。
化学品・原料:ロット管理とSKUの境界が重要な分野
化学品・接着剤・樹脂ペレットなどを扱う製造業では、有効期限や製造ロットの管理が欠かせません。このとき必ず出る質問が「ロットごとにSKUを分けるべきか?」というものです。
結論から言えば、SKUにロット番号を含めるのは避けるべきです。ロットが変わるたびにSKUが増える仕組みにしてしまうと、マスタが膨張し、在庫集計や計画調整が困難になります。多くのWMSや生産管理システムは、SKUとは別にロット管理機能を持っているため、SKUはあくまで仕様を識別する単位に留め、品質やトレースを担うロット情報は別軸で管理するのが正しい運用です。
SKUに関するよくある質問(FAQ)
Q1. SKUとは何ですか?
A. SKUは「Stock Keeping Unit」の略で、日本語では「在庫保管単位」と呼ばれます。商品をサイズ・色・入り数・パッケージなどの条件で細かく区分し、それぞれに固有のSKUを設定することで、最小単位で在庫を管理できます。
Q2. SKU管理を効率化する方法はありますか?
A. SKUをエクセルや紙で管理すると情報更新の遅れやミスが発生しやすく、SKU数が多い業種では限界があります。効率化には在庫管理システムを導入し、SKU単位の在庫をリアルタイムで可視化することが有効です。自動発注やIoT連携により、SKUごとの在庫数を正確に把握し、在庫不足や過剰在庫を防ぐことができます。
Q3. SKUの桁数に制限はありますか?
使用するシステムによりますが、一般的には13〜20桁以内が推奨されます。 あまりに長すぎると、バーコード化した際に横長になりすぎて、バーコードリーダーで読み取りにくくなるトラブルが発生します。
もう膨大なSKU在庫を数えない。スマートマットクラウド

SKU毎の在庫管理におすすめなのは、現場のあらゆるモノをIoT重量計により見える化するシステム「スマートマットクラウド」です。
1SKUに1マットで管理するため、管理画面を開けばひと目でどのSKUがどれくらいあるのかリアルタイム在庫が分かるため、わざわざ倉庫や保管場所・バックヤードに足を運んで何が・どれだけあるか確認する必要はもうありません。
自動発注も可能で、定期発注方式・定量発注方式の双方に対応できます。
IoT重量計であるスマートマットの上に管理したいモノを載せると設置が完了。あとはマットが自動でモノの在庫を検知、クラウド上でデータを管理・個数や割合を算出し、適切なタイミングで自動発注してくれます。
自動発注とはどのように行う?
納品リードタイムや安全在庫を考慮して予め発注点となるしきい値を設定できます。閾値を下回れば、自動でSMCが発注。発注先の形式に合わせた文面でメール・FAXの送信が可能です。
自動発注を利用しない場合は手動発注への切り替えも可能。その場合は、閾値を下回れば発注アラートが送信されます。
適正在庫に貢献し、キャッシュに寄与
発注や消費の推移を把握できるグラフを単純な操作で作成可能。推移グラフにより適切な在庫量を判断し、在庫圧縮を促進。不動在庫や過剰在庫を抑え、キャッシュの正常化にも寄与します。
置く場所を選びません
スマートマットはサイズ展開も豊富。厚みもなくケーブルレスで、冷蔵庫・冷凍庫利用も可能で、A6、A5サイズは小ラックや引き出しにも設置できます。さらにマルチマット使用で数百kg以上の重量物にも対応可能です。
API・Webhook・CSVでのシステム連携実績も多数
自社システムや他社システムと連携を行い、より在庫管理効率UPを実現します。